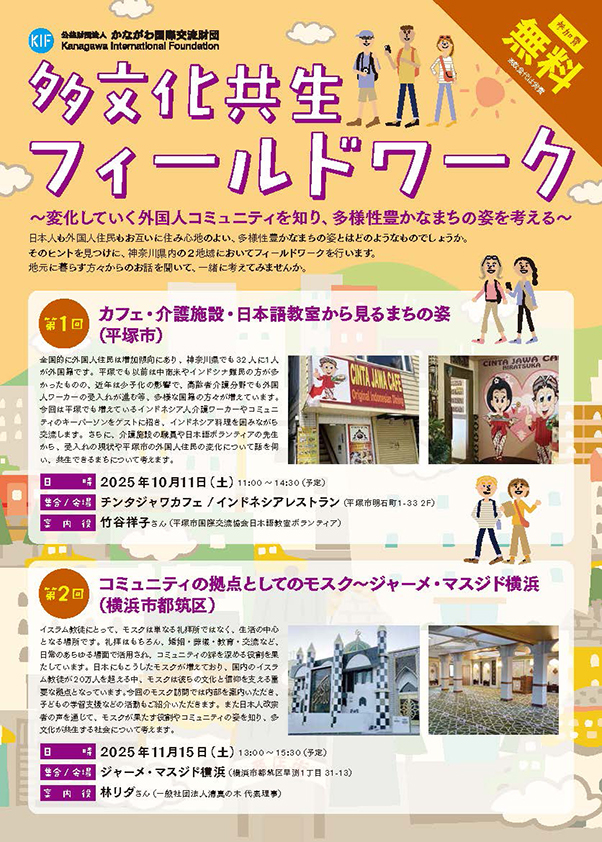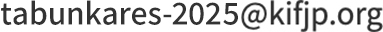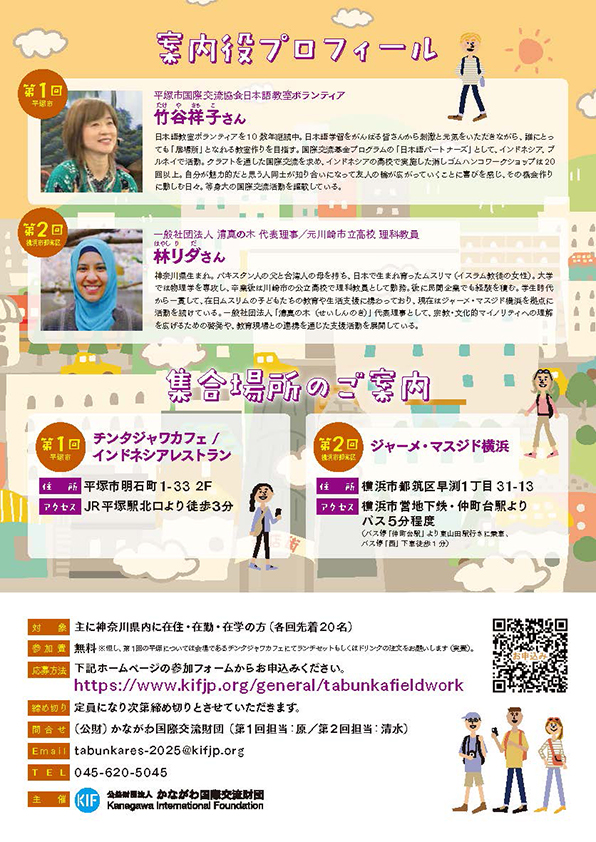Multilingual translation
KANAGAWA INTERNATIONAL FOUNDATION website can be translated into other languages, using the Google translation service.
Since the Japanese version of this website will be mechanically-translated by using a program, the results are not always 100% accurate.
See Here Google Terms of Service
Continue to browse the page https://www.kifjp.org/general/tabunkafieldwork with Google Translator Tool